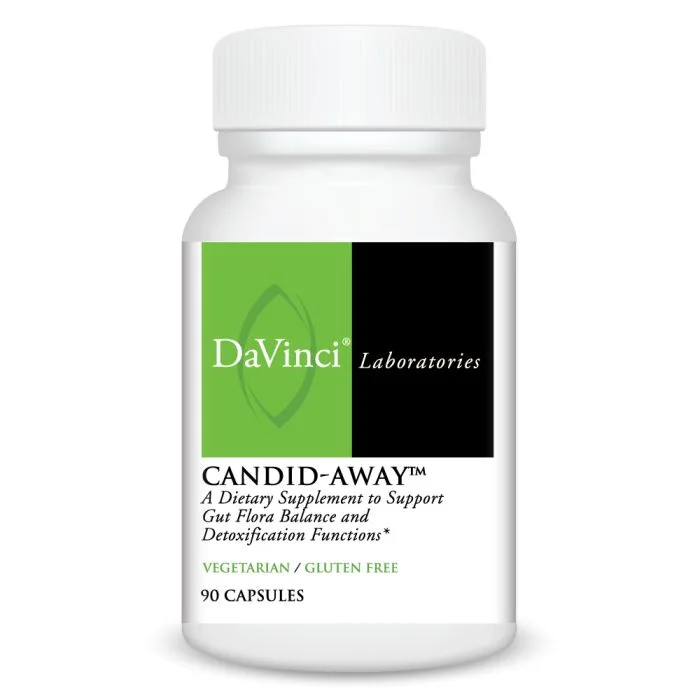とある医師の専門雑誌があるのですが、そこの記事があまりにも気になったので、書きました。
開業医の先生が書かれた記事で、内容は「他院で副腎疲労治療中の患者さんがコートリル(ステロイド剤)が切れたので処方して欲しいとやってきたが、ステロイドを簡単に処方するわけにもいかず副腎疲労という病気を調べたら、Pubmed で adrenal fatigue doesnt exist. という論文に突き当たり、この病気の存在自体が怪しい。また、副腎機能低下ということで、患者さんに聞いてみたら血中ATCHをフォローしている訳でもないし、こんな怪しい副腎疲労外来と言う看板を掲げてる医者は大丈夫か?」というものです。
私が日本で副腎疲労外来を始めて15年になりますが、「副腎疲労外来」はとても増えたと思います。
中にはこのように表面上のことだけを理解して、コルチゾールの検査をせずに、ステロイドを処方してしまう先生もいるようですが、これが極端にひどい例であることを祈ります。その雑誌に書かれた先生のツッコミももっともだと思いますので、副腎疲労の概念、診断、治療に最低限守るべきことを書いておきます。
1 副腎は疲労しない(正式にはストレスによるHPA軸の障害である)
2 ちゃんと診断しよう(除外診断も重要)
3 ステロイドは用いない
1 副腎は疲労しない
副腎疲労(Adrenal fatigue)は1990年代にカイロプラクターのJamesWilson博士により提唱された概念です。長年のストレスにより副腎が疲弊しコルチゾール分泌が減弱するというものです。 しかし、実際に副腎が疲弊する事実はありません。Pubmedの論文の記載通りです。
長年のストレスや慢性炎症などにより高コルチゾールが継続すると、下垂体から放出されるATCHのネガティブフィードバックのセットポイントが下がってきます。コルチゾールは体蛋白を異化させ、海馬を萎縮させるので、それを防ぐためかと思われます。
ついには、ACTH低下のためにコルチゾールも基準範囲を下回るようになります。これが俗に言う副腎疲労のステージ2です。つまり副腎疲労というのは言うなれば下垂体疲労なのです。 HPA軸(視床下部-下垂体-副腎)で言えば、視床下部からのCRHに下垂体からのACTHと副腎のコルチゾールが反応しない状態であり、正式な医学的名称はHPA-axis dysfunctionになります。
このHPA軸障害をpubmedで検索すると、うつやPTSDなど慢性ストレスを引き起こす疾患との関連論文が多数ヒットします。
(じゃあ、なんで副腎疲労外来と言う名前を残しているかというと、患者さんが理解しやすいからです。HPA軸の説明は難しく説明に時間がかかる。副腎が疲れると言うのは説明がしやすい。increased intestinal permabilityではなくリーキーガットを使うのと同じです。)
2 ちゃんと診断しよう(除外診断も重要)
HPA軸障害は下垂体性の低コルチゾール症で、器質性の下垂体腺腫やアディソン病などとは全く性質の違うものですが、時に重症化するとアディソン病などに類似した症状を呈することもあります。
だからと言って、慢性疲労や朝が起きられない、うつや「やる気のなさ」などの症状のみから診断を付ける事は殊に避けなければなりません。
HPA軸障害で低下するコルチゾールレベルは僅かなので、血中よりも唾液中レベル測定が適しています。
症状によっては内分泌専門科の受診、下垂体や副腎のCT検索などを併せて行うべきであり、そうでなくとも最低限血中のACTH、コルチゾールなどは検査し、基準値以内であることを確認すべきです。
3 治療にはステロイドを用いない
副腎疲労(HPA軸機能障害)は、慢性ストレスの結果HPA軸がダウンレギュレーションを起こした状態です。器質的な障害、下垂体の血流低下や副腎の萎縮などはなく、よほどの極期を除いて、ステロイドの使用は避けるべきです。
実際の治療は、HPA軸のストレス負荷を軽減した状態で、ステロイドを用いずに滋養強壮の生薬やホルモンの前駆体などを用いてコルチゾールレベルを修正していきます。
副腎の疲労を治すのではなく、歪んでしまったHPA軸を元に戻すのです。副腎疲労の治療のポイントは脳へのアプローチにあります。
実は、副腎疲労の診断で検査も受けず、ステロイドだけ処方されてる方、時々うちにもいらっしゃいますが、殆ど治ってないです。患者さんに良かれと思って投薬されているのでしょうが、ステロイドの離脱の分だけ余計に時間もお金もかかります。
中途半端でない系統的な治療にぜひ切り替えを!