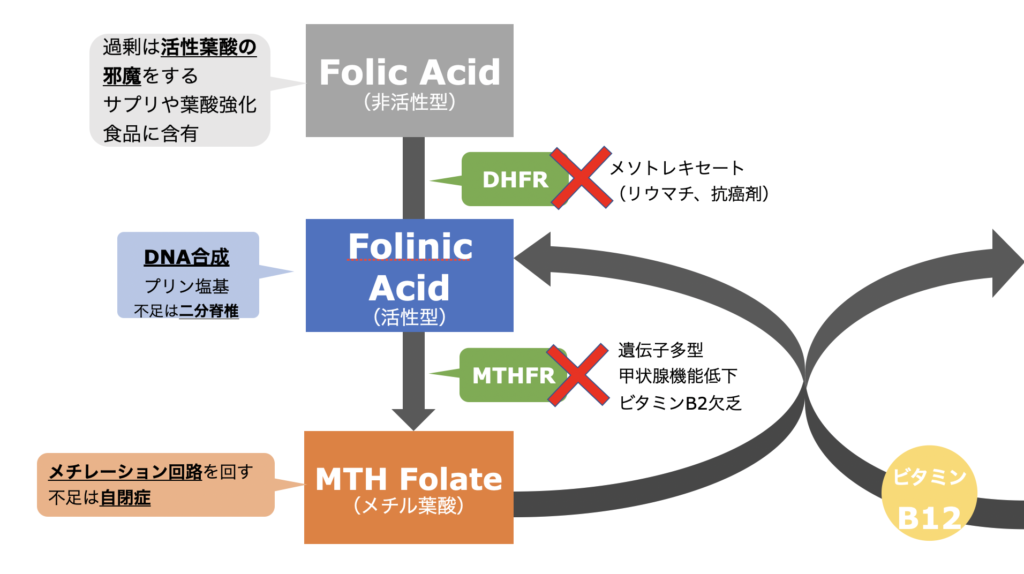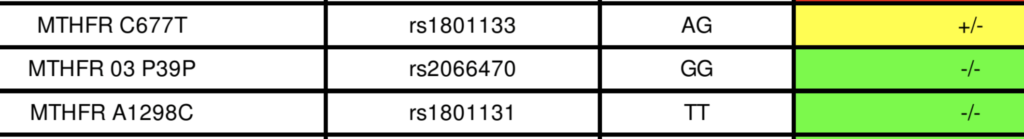7月末は、多くの方から講座のご質問をいただく時期ですが、その中でも一番多いご質問についてお答えします。
その質問とは、これです。
「カウンセラーは、医師のようにデータを読んで診断したり、治療サプリを処方したりできないとの事ですが、じゃあ何ができるのでしょうか?」
答え
カウンセラーの仕事は、クライアントに解決策を直接提示する事ではありません。
クライアントが自らに向き合い、自分なりの理解に自発的にたどり着き、その結果、自分の問題に対応できるように導いてあげる事です。
で、この導くというのはとても重要な事なんです。なぜなら、栄養療法の成否は、患者さんのモチベーションで決まるからです。
栄養療法、どっちの方が結果が出やすいと思いますか?
A 患者さんを診断して、摂るべきサプリや食事方法を指導する
B 患者さんに自己診断の方法を教えて、自分で摂るサプリや食事を自分で決めてもらう
自分の頭で理解し、腑に落ちた治療法へのモチベーションは、単純にこれ飲んでと言われた場合と比べものになりません。
頭ごなしに「明日からグルテン、カゼイン、カフェイン、アルコール、精製糖質を完全に抜いてください。」と言われてもできる人はほとんどいないでしょう。
その一方で、「グルテンがゾヌリン蛋白を分泌させ、ゾヌリンが腸のタイトジャンクションを開いてしまうため、大量の異物が腸を通り抜けて体内に炎症を引き起こす事」、「自分の症状がそれから起きている可能性がある事」を理解できれば、グルテンを一定期間止めるのはそれほど大変な事ではないでしょう。
はっきり言って、診断治療よりカウンセリングの方が難しいです。
「あなたはB6とCとマグネシウムが足りないので、サプリで補給してください。」というのは簡単。
「足りない栄養と、症状を自覚させ、自らが対処できるように導いてあげる」ていうのは大変。
自分の検査結果を深く理解し、自分の体の声に耳を傾け、様々な食事やサプリを試行錯誤しながら試してみる。
そのようにして分子栄養学を深く理解しないと、カウンセリングはできません。
だからこそ、その場で簡単にできる診断法のような薄っぺらいことは教えていません。
基礎講座で三大栄養素の代謝からきっちり学んで、考え方のフレームワークを作っていただくように、骨太な講義になっているし、ズーム検討会で、他の方の自己分析結果を聞く事で、自らの気づきを促す訓練をしていただいているのです。
自ら「気づき」を得る事が、自分のクライアントにどのように気づきを起こさせるかの重要なヒントになります。
これは栄養療法を行う医師にとっても重要な事で、治療の成果は患者さんの食事や生活習慣のコンプライアンスをいかにあげるかにかかっていますが、それはどのように気づきを与えるかと同じ事を意味しています。