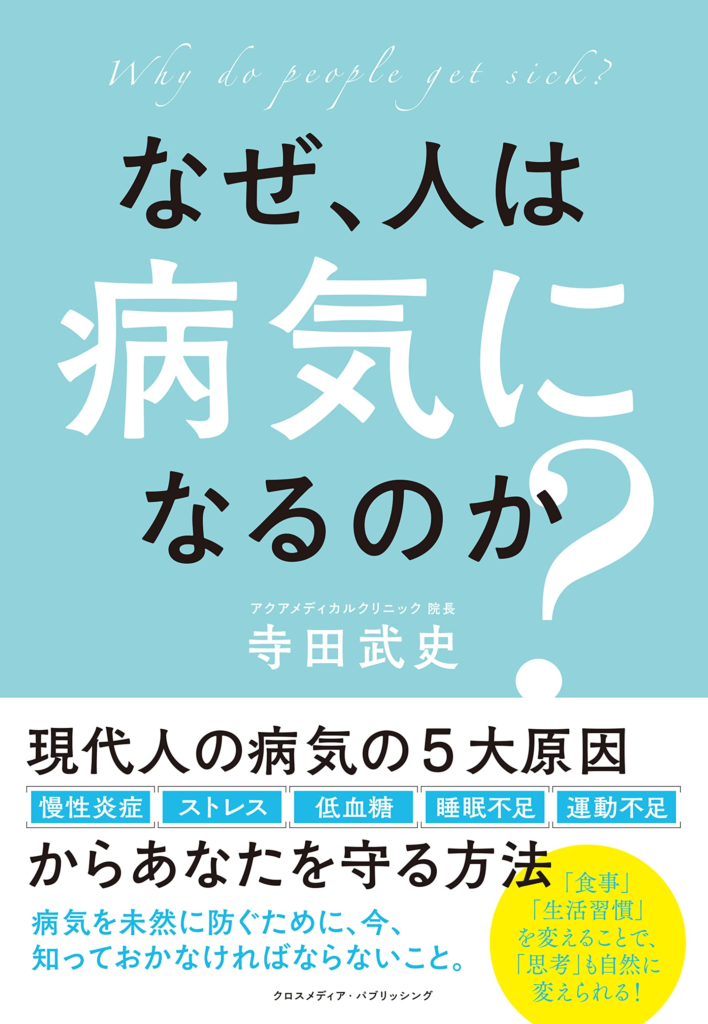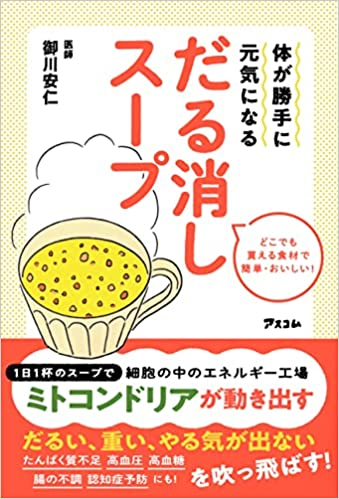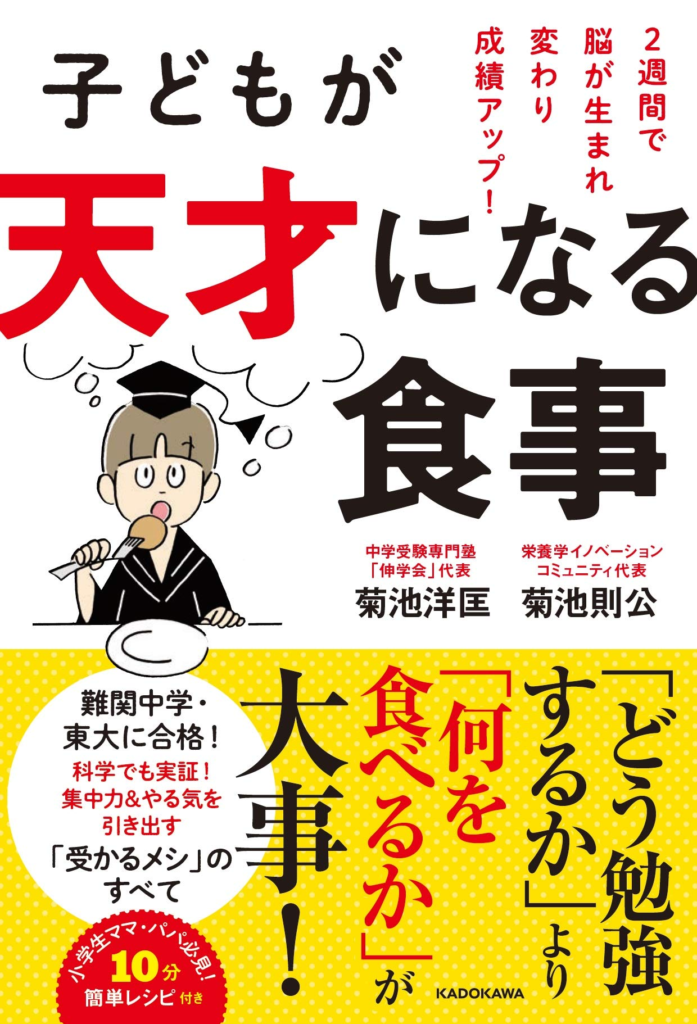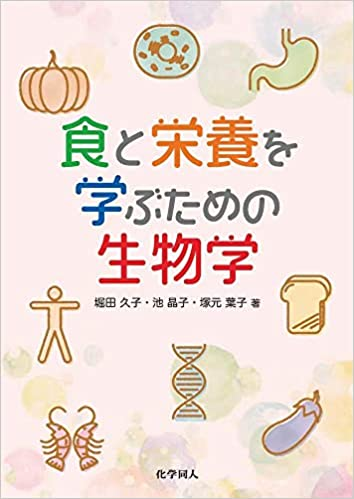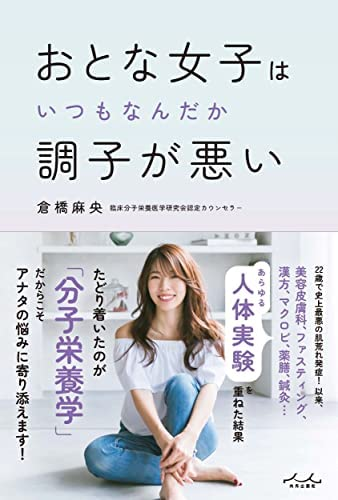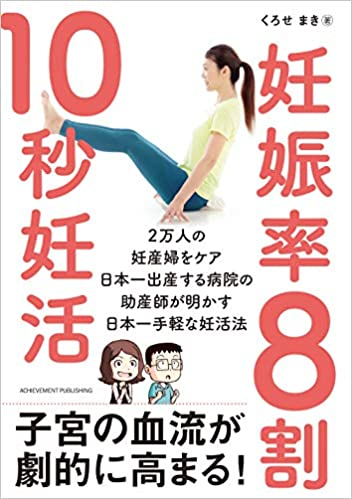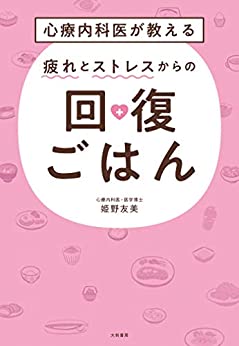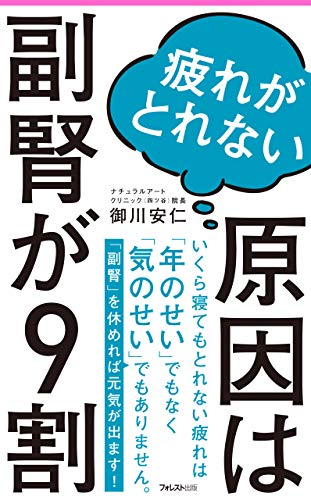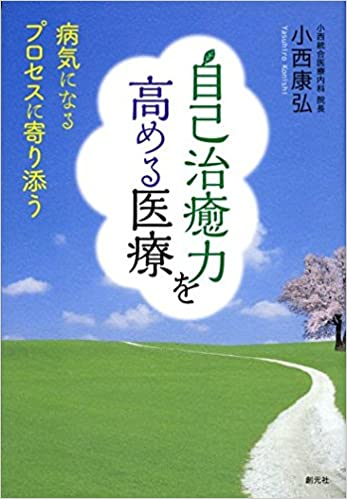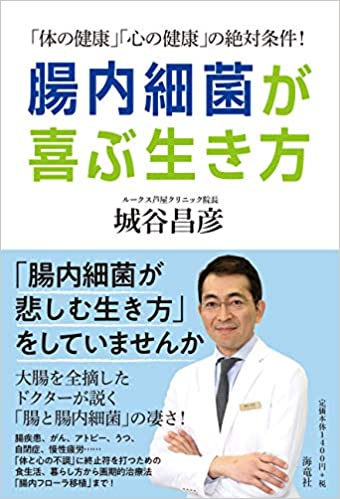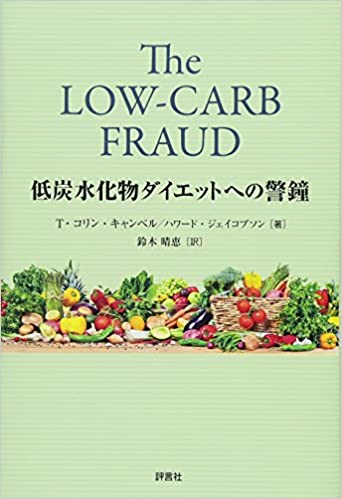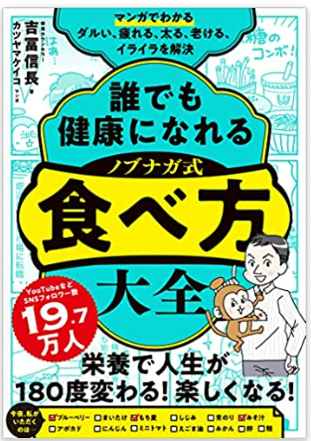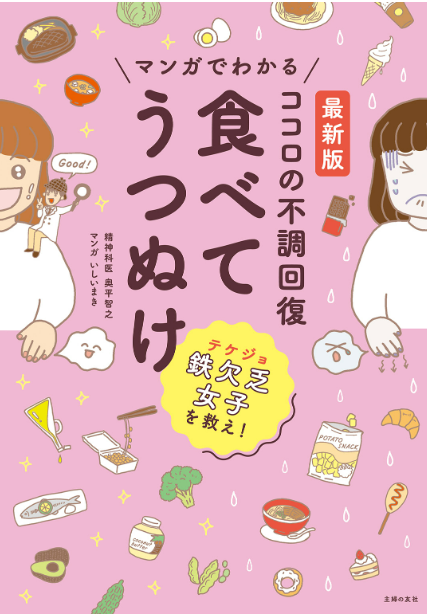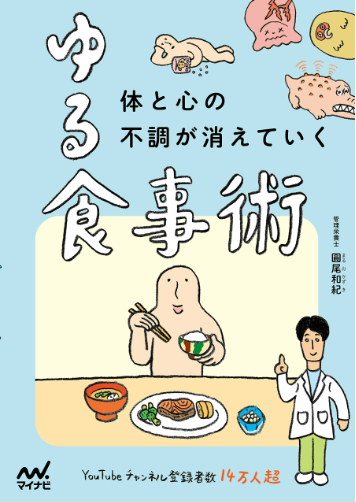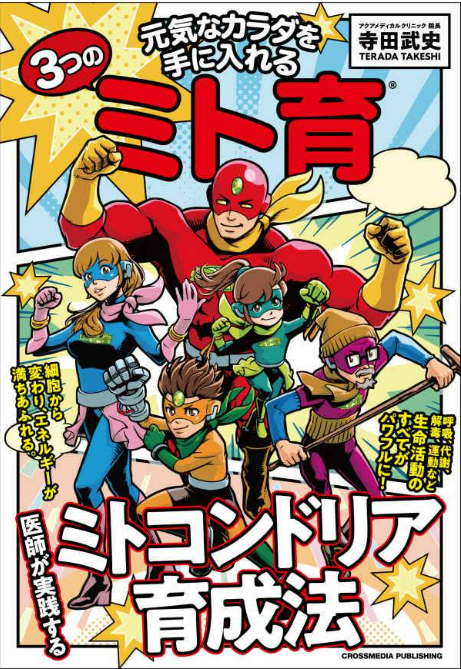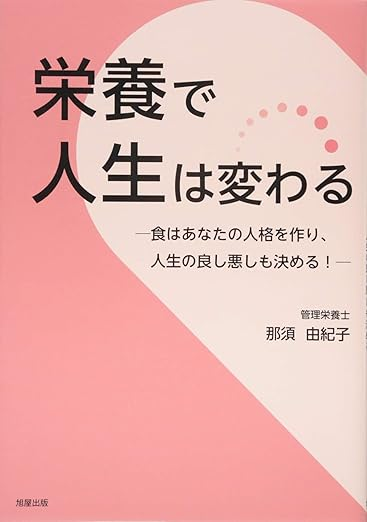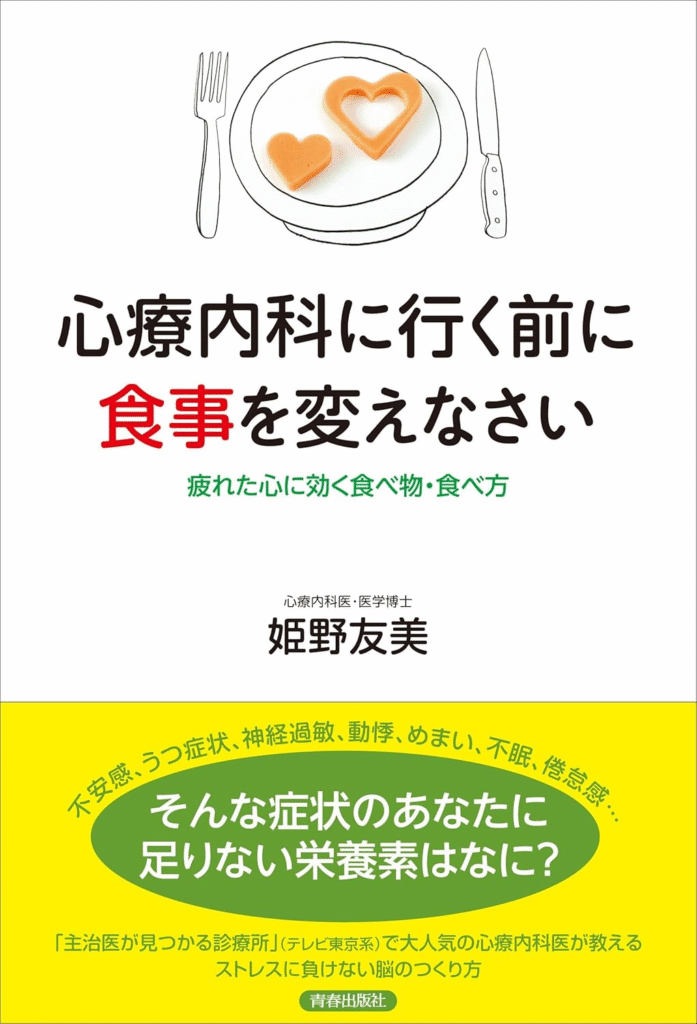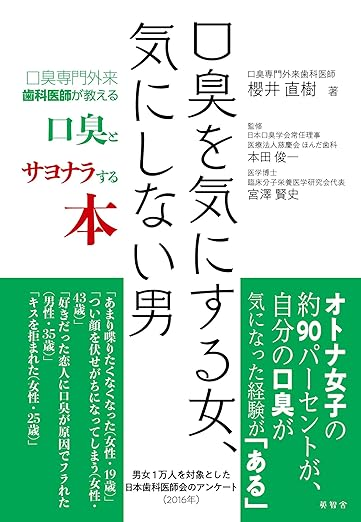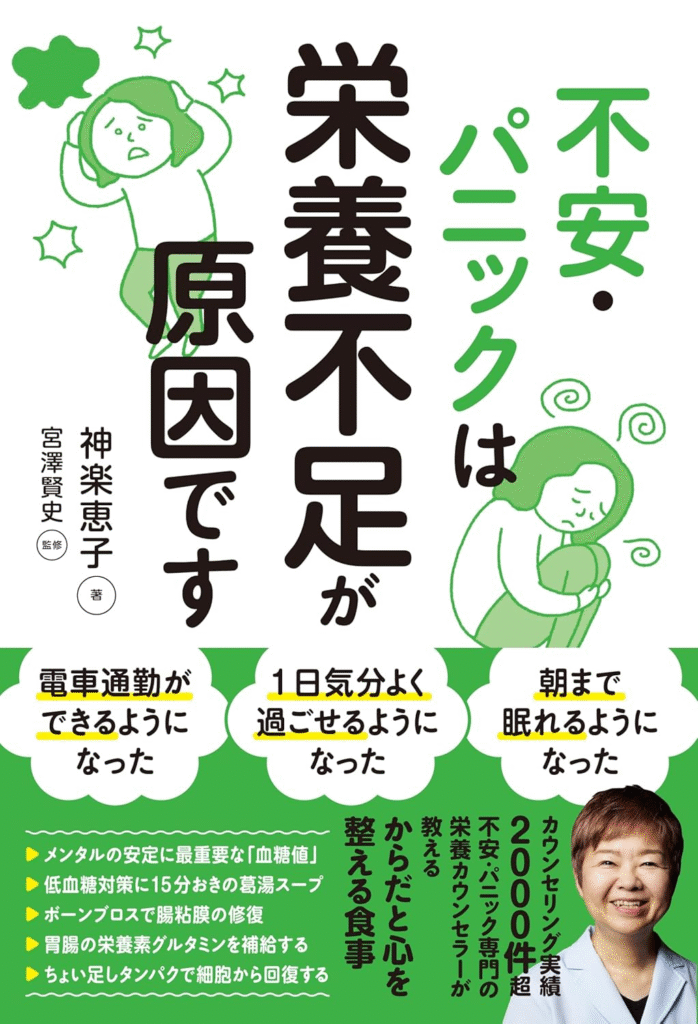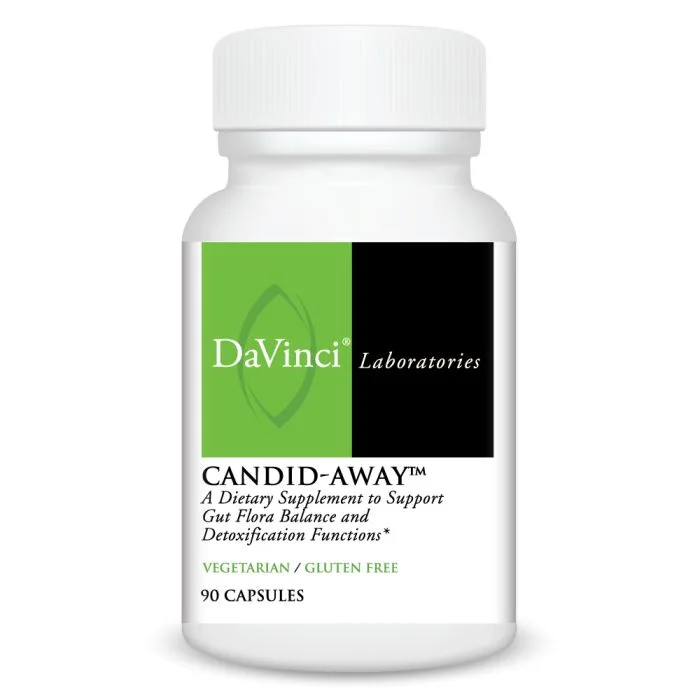臨床分子栄養医学研究会では様々なご要望に応じて、多種類のアドバンスコースを公開しております。
栄養療法セルフケアコース
栄養療法で自分を知るためのセルフチェックを詰め込んだオンライン・コースです。
栄養療法をマスターするには、まず自分を知ること(自分の根本原因をチェックし、治療方針を組み上げてみる)のが一番早道です。
4つのステップに分けて分かりやすく解説しています。
- ステップ1 自分に問診する(当てはまるものにチェックをつけるだけ)
- ステップ2 検査をして確かめる(血液、毛髪、有機酸検査の結果を見ながらチェックするだけ)
- ステップ3 自分に必要な治療を選ぶ(ステップ1、2の結果から総合判定票を埋めて、次に治療アクションシートにチェックをつけるだけ)
- ステップ4 順番に治療する(治療順番チャートに書き込むだけ)
5分程度の短い動画で構成されていて、「これを知りたい」というピンポイントな知識習得に役立ちます。
まごめじゅん特選オンラインコース
分子栄養学実践講座でも大人気のまごめじゅん先生が過去に行っていたコンテンツをまとめてご覧いただけます。
コンテンツは全16本
栄養療法って何?、一般的な医療とどう違うの?
エネルギー代謝などの回路など、一般の方が普段聞きなれないカタカナやアルファベットが満載の専門用語を並び立てても、伝わりません。
栄養カウンセラーを目指している方や今後、栄養セミナーをしたい方にぴったりな、患者さんや生徒さんにわかりやすくお伝えする際のコツもそれぞれの動画で触れられています。
小池アドバンス
血液検査の深読みと分かりやすい解説でおなじみの小池雅美先生によるアドバンスコースです。
月に1回ZOOMにて講義と症例解析を行っています。
解析する症例は参加者による持ち寄りですので、「小池先生に解析してもらいたい!」という方におすすめです。(WEB版は講義部分のみを配信しますので、症例解析への参加はできません)
講義は子育てから栄養素に至るまで毎回違うテーマを幅広く扱っています。
アドバンスと書いてあるため敷居が高いと思われがちですが初心者さんも大歓迎です。
鹿沼聡美の薬膳のすゝめ
美養薬膳研究家 鹿沼聡美先生の「分子栄養学」と「薬膳」を融合させたオンライン料理教室です。
毎月1回薬膳や東洋医学に関する講義と、薬膳を身近に感じていただき、日々の献立にとり入れやすい「簡単」で「美味しい」薬膳料理をご紹介していきます。
副腎疲労やお疲れの方は日々のお料理もなかなか大変です。
本当に簡単で美味しい料理を紹介しますので、日々の献立にお役立てください。
~こんなことをやってきました(一部抜粋)~
薬膳の基礎理論を腹落ちさせよう!今すぐ使える舌診(実習:簡単すぎるのに褒められる「うま塩肉じゃが」&秒速でできる副菜
「五臓」は「感情」で理解する!カウンセリングで使える東洋医学(実習:グルテンカゼインフリー!アレンジ自在の簡単「スパイスカレー」)
大野真理の難しすぎない分子栄養学オンラインセミナー
- 分子栄養学の基礎を簡単に説明してほしい
- 分子栄養学を他の人にも勧めたいけど難しいと思われる。
- クライアントにうまく説明できない。
など思う方は少なくありません。
この講座では、分子栄養学を初めて学ぶ方にもわかりやすくクライアントに説明するときに参考になるようなコンテンツを公開していきます。
毎月第3木曜日10:00からZOOMにて開催します。(動画公開もしますので見逃した方も安心です)